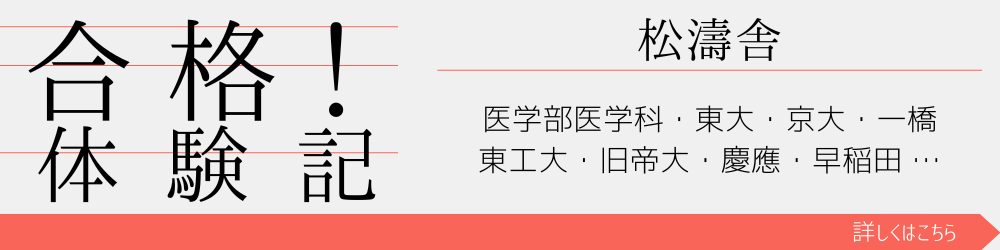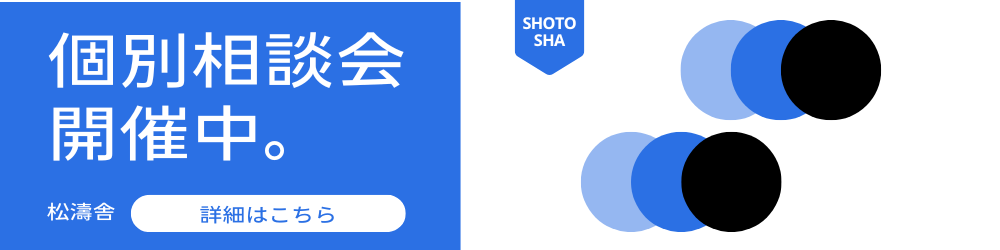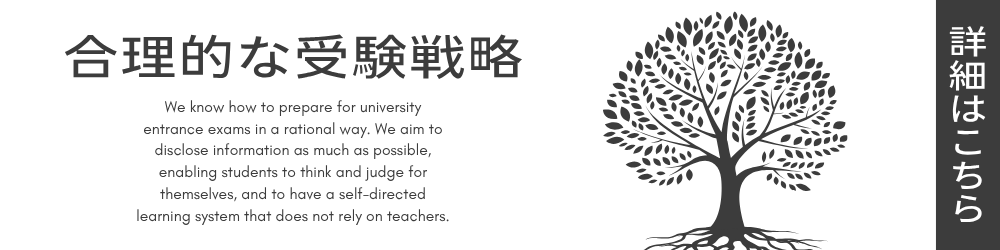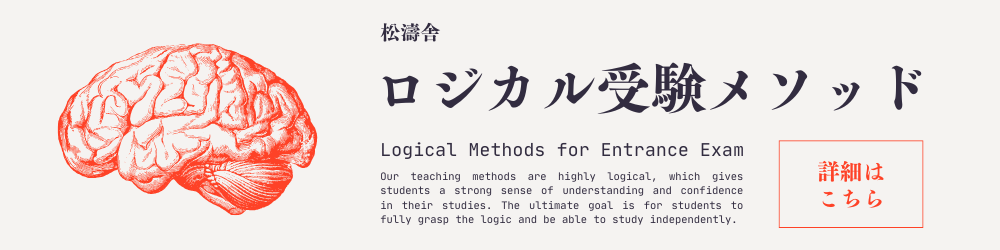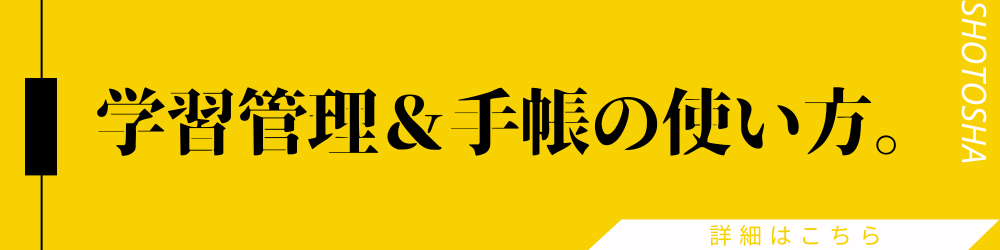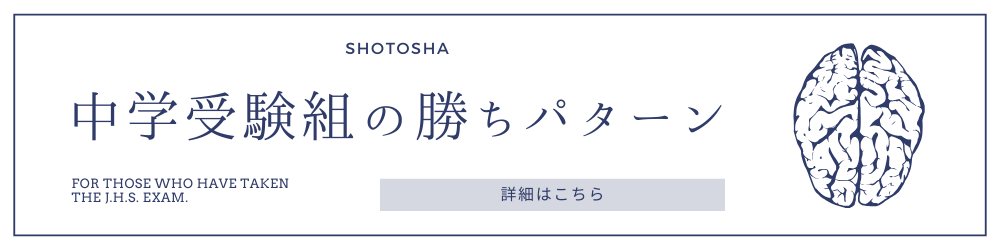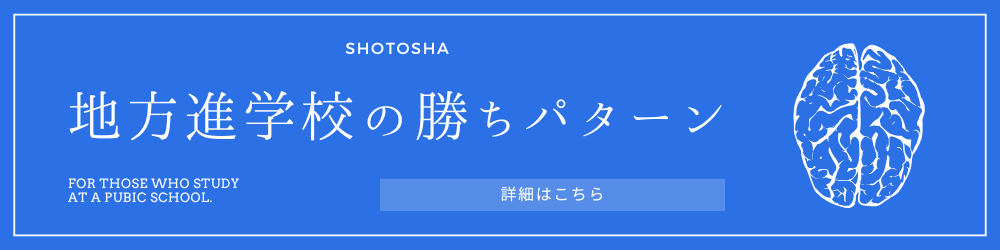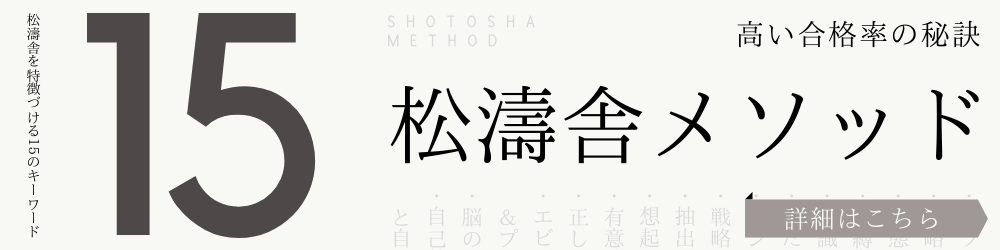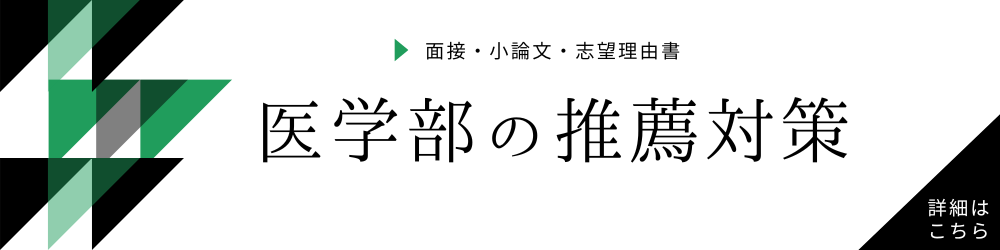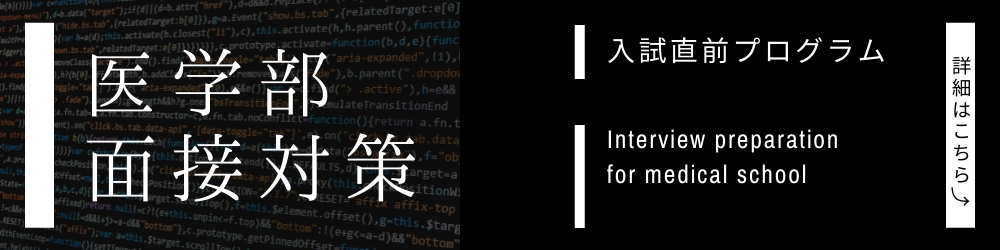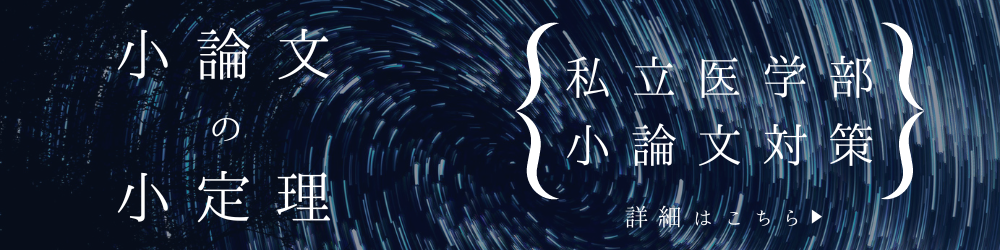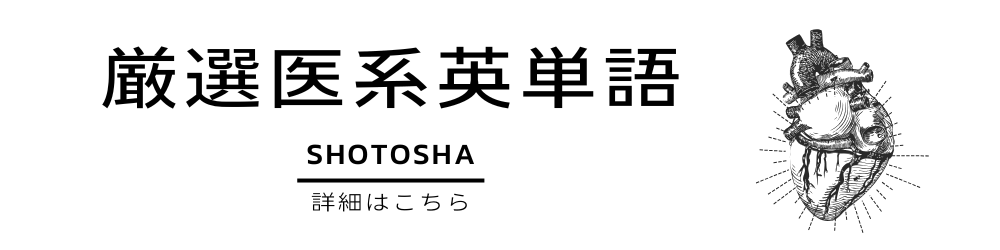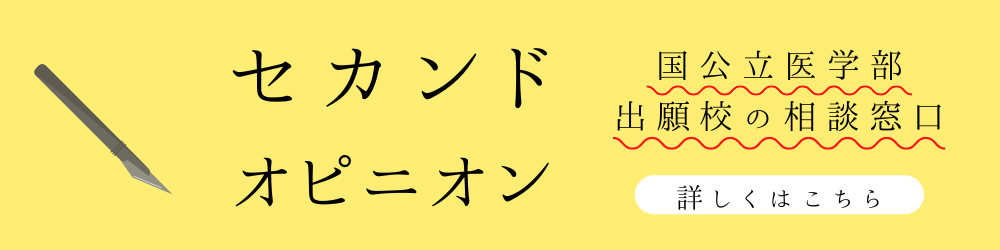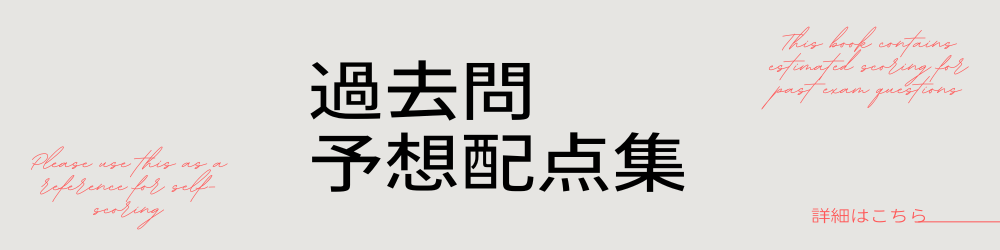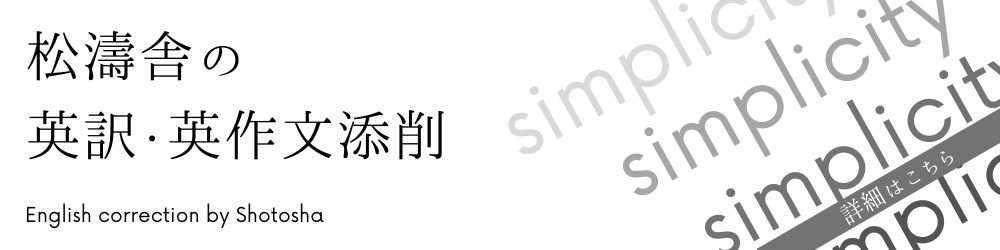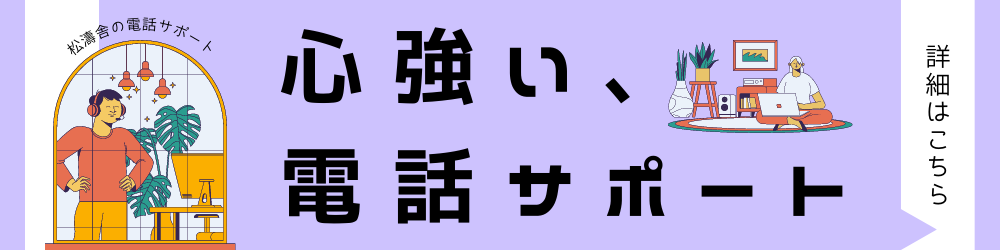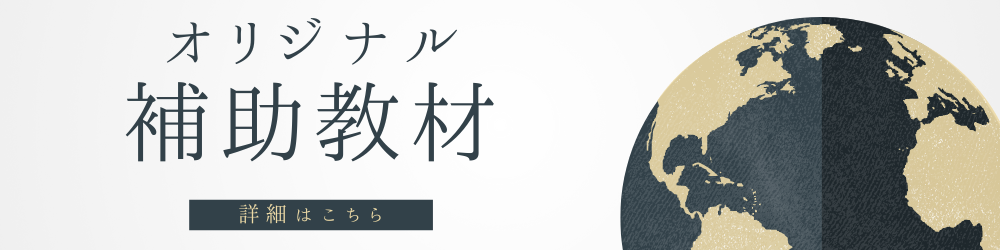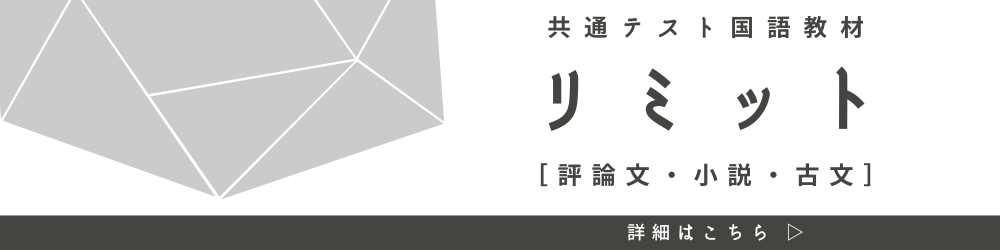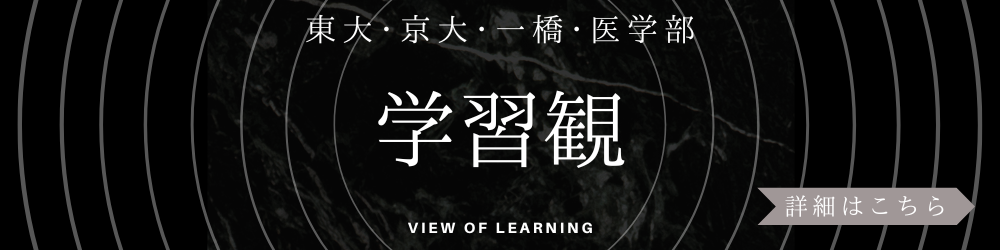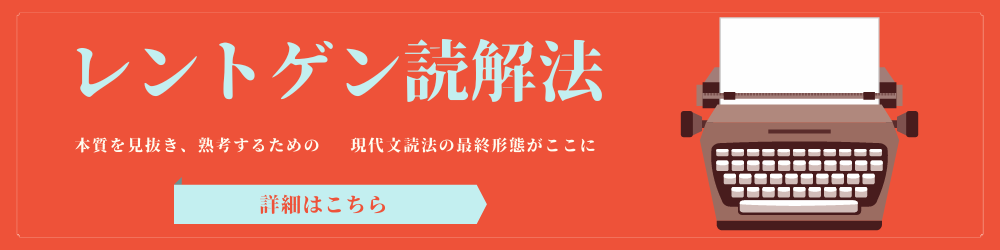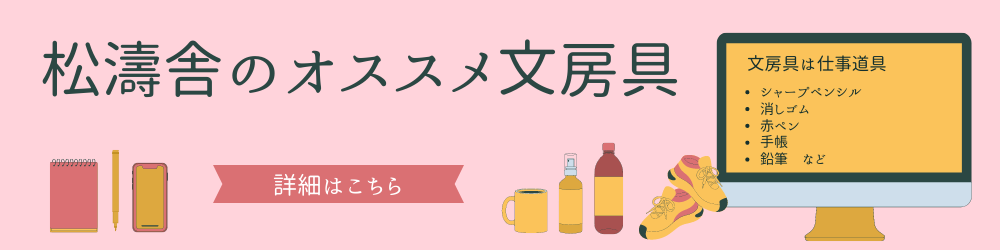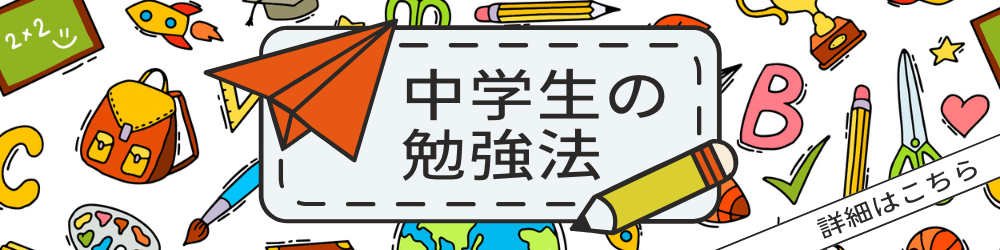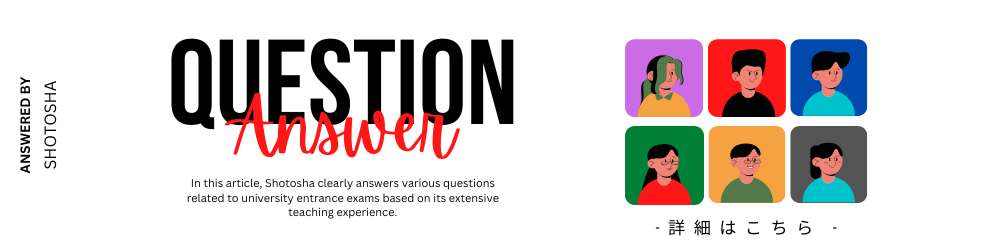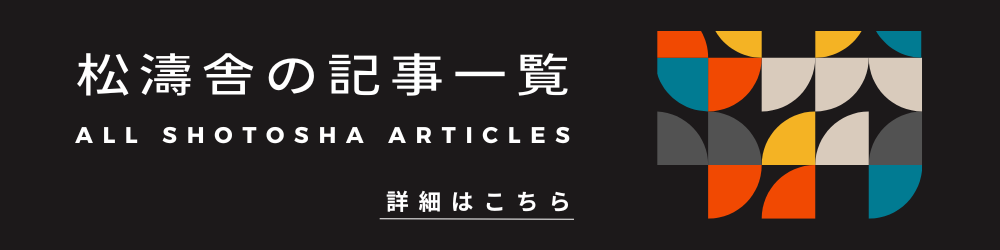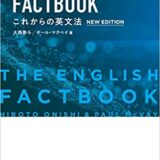受験勉強の大敵は「妄想」です。
「上位校合格者はもともと頭が良く、努力せずに高得点が取れる人」
「高い目標を掲げ、そこに向かってポジティブに勉強できる人」
と考えがちですが、それは妄想です。
勝手に作った「合格者像」と照らし合わせ、そうではない自分には無理だと考えてしまうことが、誤った判断につながります。
ここでは上位校合格者の現実をいくつか列記し、勝手な妄想による不利益を被らないようにしてもらえたらと思います。
高い目標を掲げてはいない
上位校合格者は、小さな頃から神童で、上位校(東大や医学部)に入ることを夢見て勉強していると思われがちです。
しかし、多くは高校2,3年生で進路を決めるまでは明確に目指しておらず、進路決定のタイミングになって「君の成績なら東大や医学部に行ける」と言われて意識するようになっているのが現実です。逆に、東大や医学部は雲の上の存在で自分には無理、と思っている人のほうが多いのです。
大事なのは、進路決定の段階で上位校を目指せるだけの十分な知識(≒基礎知識)が身についていることです。上位校合格者が基礎知識を身につけられる理由は、地頭が良いからではありません。
直近にやるべきことが明確だからです。
直近にやるべきことが明確
地方進学校出身者と首都圏中高一貫校出身者に共通しているのは、直近でやるべきことが明確であるということです。
地方進学校や首都圏中堅中高一貫校では、定期テストという直近のマイルストーンに向けて勉強している人が多いです。学校の定期テストで良い成績を取るべく適切な問題集を繰り返した結果、必要な学力が結果的に身についている、というパターンです。
ただし、多くの高校では上位校の合格には足りない量・レベルの問題集しか指定されないため(平均値・中央値に合わせて問題集が選定される)、自分で補う必要があります。
首都圏中高一貫校で多いのは、鉄緑会など大きな実績を出している塾の宿題や、学校内に存在している「この時期には、この問題集をやっておけばOK」といった情報が、直近やるべきことを明確に規定しています。
直近やるべきことをひたすらこなしていったら、いつの間にか必要な知識量を超えていた、というのが現実なのです。
いわば、上位校は狙って合格できるものではなく、結果的に狙える状態になっていると言えます。
確かな手応えを掴んでいる
直近やるべきことが明確だったとしても、結果が出なければ継続はできません。
直近やるべきことをきちんとやった結果、校内順位を高くキープできていたり、外部模試の全国順位が十分なレンジに入っているといった、確かな手応えを掴んでいます。
塾や学校に言われたことをやり続け、結果も手応えも得ないまま同じ宿題を続けたり、同じ塾に通い続けることを、上位校合格者はしていません。
正しい方法で勉強したときには成績が伸び、間違えた勉強方法をしたときは結果が出ないというフィードバックを得て、正しい方法に修正しながら勉強を継続しています。
理解できる(ハックできる)と感じる瞬間がある
上位校合格者ははじめから全教科の全分野に不得意科目がないと思いがちです。しかし、誰でも苦手な教科があり、つまずいた分野があります。
共通しているのは、ある分野のある問題に対して強烈に納得した(理解した)経験を持っているということ。
例えば、ベクトルを強烈に理解したことによって数学全体に対する苦手意識が減ったり、日本史のとある事象の因果関係に強烈に納得して経験から日本史が理解可能なものであると感じた経験をしています。
すべての分野が初めからできる必要はありません。たった1つの分野でも良いので強烈に納得・理解する経験が、全体に対する得意意識に繋がる経験をしている人が多いです。
これは、やるべきことを淡々と継続した人だけが得られる経験とも言えます。
ここまでをまとめると、やるべきことが明確で、結果も出ていて、さらにどこかのタイミングで、とある分野において強烈な腹落ち感を経験している、という共通点があります。
ネガティブなモチベーションを持っている
勉強が好きな人でなければ上位校に合格できない、という考えもまた妄想です。受験は総合点で合否が決まりますが、すべての教科が好きで得意な人はほとんどいません。
嫌いな科目に対してはネガティブなモチベーションで勉強している人が多いのが事実です。
ネガティブなモチベーションとは「成績を落としたくないから頑張る」「誰々に負けるのは嫌だから勉強する」といった、自分にとって居心地の悪い状態に陥らないようにする原動力のことを指します。
「成績を伸ばそうと頑張ること」と「成績が落ちないように頑張ること」は違います。
前者のように高い目標に向けて勉強できる人は問題ないですが、後者のような弱い(が実は本質的でもある)モチベーションの人も、上位校を諦める必要はありません。そういう人の方が合格者には多いからです。
激しく落ち込みはするが、やるべきことを淡々とできる
「悪い成績を取って落ち込んだことのない強靭な精神力を持った人だけが上位校に合格している」と思わないでください。
上位校合格者でも、模試の結果が悪いことはよくあります。
そして、めちゃくちゃ凹みます。
十分な時間をかけて勉強したと認識しているのに結果が出ないのは当然辛いですから、勉強をしていない人よりもかなり落ち込みます。
しかし、落ち込むか、落ち込まないかは合否には関係ありません。落ち込んでいる時間は知識量を増やすことに貢献していないから、やるべきことに戻ろうと思っているだけです。
ただし、模試の結果によっては大きく不安になることもあるため、受験期には信頼できるパートナーや先生、先輩に相談できるようにしておくと良いでしょう。
最後に
日々の学習に強い納得感を持ちつつ、その過程を通して小さな成功体験を重ねていってください。これが結果的に上位校合格につながっています。
変な妄想をして不必要に自信を失ったり、諦めたりすることはしないようにしましょう。大事なのは、遠くを見たり、周りを眺めるのではなく、足元のやるべきことに焦点を当てることです。
それだけ、今やるべきことに強烈に納得できている状態が理想だということです。
「【決定版】上位校合格者の現実」に関するQ&A
- 上位校合格者はどのような勉強法を実践しているのか?
- 上位校合格者は、直近の目標を明確にし、定期テストに向けた勉強を重視しています。適切な問題集を繰り返すことで、必要な学力を自然に身につけています。
- 高い目標を掲げることは重要なのか?
- 上位校合格者は必ずしも高い目標を持っているわけではありません。多くは進路決定時に意識し始め、基礎知識を身につけることが重要です。
- どのようにして確かな手応えを得るのか?
- 定期的な模試や校内順位を通じて、勉強の成果を実感します。正しい方法で勉強した結果、成績が伸びることで自信を持ち続けることができます。
- 苦手科目を克服するためのポイントは?
- 上位校合格者は、特定の分野で強い理解を持つ瞬間を経験しています。この理解が他の科目への苦手意識を軽減し、全体の成績向上に繋がります。
- ネガティブなモチベーションは受験にどう影響するのか?
- ネガティブなモチベーションは、成績を落とさないための原動力となります。嫌いな科目に対しても努力することで、合格を目指すことが可能です。
- 落ち込むことは悪いことなのか?
- 上位校合格者でも模試の結果に落ち込むことはありますが、それを乗り越え、やるべきことに戻ることが重要です。感情をコントロールし、勉強を続ける姿勢が求められます。
- どのようにして日々の学習に納得感を持つのか?
- 日々の学習に納得感を持つためには、自分の進捗を確認し、小さな成功体験を重ねることが大切です。これが最終的な合格に繋がります。
- 上位校合格者に共通する特徴は何か?
- 上位校合格者は、やるべきことが明確で、結果を出し、特定の分野で強い理解を持つ経験を共有しています。これらが合格の鍵となります。
- 受験生が陥りやすい妄想とは?
- 受験生は「上位校合格者は特別な才能がある」と考えがちですが、実際には多くの努力と正しい方法が必要です。妄想を捨て、現実を見つめることが重要です。
- 受験勉強で最も大切なことは何か?
- 受験勉強で最も大切なのは、目の前のやるべきことに集中し、確かな手応えを得ることです。遠くを見ず、足元をしっかりと見つめる姿勢が成功に繋がります。