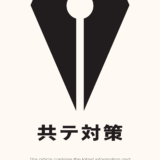目次
- 共通テスト英語のリーディングの解き方にコツはある?
- 共通テスト英語のリーディングの解く順番
- 共通テスト英語のリーディングの時間配分
- 共通テスト英語のリーディングで時間切れを防ぐ方法
- 共通テスト英語のリーディングの時短テクニック
- 共通テスト英語のリーディングで2択で迷った場合
- 共通テスト英語のリーディングのグラフ問題の解き方
- 共通テスト英語のリーディングでは先に問題や選択肢を読むべきか?
- 共通テスト英語のリーディングでは印をつけるべきか?
- 共通テスト英語のリーディングでスラッシュリーディングはすべきか?
- 共通テスト英語のリーディングでケアレスミスを防ぐ方法
- 共通テスト英語のリーディングの見直し方法
- 共通テスト英語のリスニングの解き方にコツはある?
- 共通テスト英語のリスニングでは最初に選択肢に目を通すべきか?
- 共通テスト英語のリスニングで集中力を持続する方法
- 共通テスト英語のリスニングで聞き逃した場合の対処法
共通テスト英語のリーディングの解き方にコツはある?
当然ですが、ベースに確固たる英語の実力がなければなりません。英語の成績(偏差値)の決まり方は以下の記事に書いた通りですが、語彙量・文法知識量・多読多聴量の3つのどれかがボトルネックになるため、すべてを上げていく必要があります。
その上で共通テスト英語のリーディングという特殊な形式の問題を解くコツはあります。それは、
①状況把握
②質問把握
③速読
この3つをスピーディーに行うことです。
①状況把握
今どんな場面で、何の資料が与えられているのかを把握することです。唐突にメール文面が与えられる、チラシの文面が見せられる・・・そんな中で素早く状況を理解し、キャッチアップする必要があります。
②質問把握
何について答えたらいいのか、問題文を見て把握することを指します。何について問われるのかがわかっていない状態で読み進めていくのは非常に効率が悪いです。質問を見て改めて文章を読み直す羽目になります。問いを確認し、その答えになる部分を探す目で読むことで、効率的に答えられるようになります。
③速読
その名の通り、スピーディーに英語を読み、理解し、問いの答えとなる部分を探すことを指します。ポイントは「日本語を介さず、英語を英語のまま理解すること」です。これは一朝一夕にできることではないので、普段の勉強からそのように英語を処理できるようになっておく必要があります。
共通テスト英語のリーディングの解く順番
大問1から順に解いていきましょう。共通テスト英語のリーディングは満点が取れるレベルです。よって、頭から全問解く前提で進めましょう。逆に言えば、二次試験のように満点を取る必要のない試験では、解く順番を工夫する必要があることが多いです。
共通テスト英語のリーディングの時間配分
大まかに決めておくとよいですが、あまり囚われすぎない方がいい、というのが結論です。
なぜなら、共通テスト英語のリーディングは出題形式や大問数、難易度が安定しない試験だからです。下手に時間配分を決めてそれに囚われ、結局その年の出題に合わずに時間が足りなくなった、といったことになる可能性があります。
コツは、大まかな時間配分を試験開始直後に決めることです。だいたいどれくらいまでに半分が解き終わっていないといけなそうかを確認するのです。
共通テスト英語のリーディングはほとんどの問題が3点で、前半に少しだけ2点、後半に少しだけ4点の問題がある感じです。よって、問題数を確認し、その半分ちょっとが終わった時点で時間の1/2、さらにその半分が過ぎた時点で1/4が終わっていたらOKと考えます。
例えば、解答番号が44まであり、大問が8つだった場合、大問5が解答番号23までなので、ここまでで試験時間の1/2(=40分)になっていたらOKと考えます。ただ半分まで時間を気にせずにいくのは怖いのと、時間に焦り過ぎないほうが集中して解けると考え、解答番号13までである大問3で試験時間の1/4(=20分)くらいであったらOKと考えます。
このように、解答番号でいいので大枠で時間配分を考えておくといいです。もちろん、後半の方が難しく、配点も高いので、前半はややタイトにしておくといいです。こういった練習も過去問演習でやっておきたいです。
共通テスト英語のリーディングで時間切れを防ぐ方法
元も子もないですが、「日本語を介さず、英語を英語のまま理解できる状態」にあることがベースで必要です。わざわざ日本語に訳してから理解しているようでは時間内に正確に解き終わることは難しくなります。
その上で、時間切れを防ぐためには、先述の通り、
①状況把握
②質問把握
③速読
この3つを意識し、パッパと解いていくことです。
また、目標点を決めておき、何問なら落としていいかを決めておくことも重要です。満点を取る必要があるなら1問も落とせませんが、85点でいいなら5問落とせます。5問ということは、16分に1問、捨てたり飛ばしたりしていいということです。結構、落ち着いて飛ばせますよね。
ちなみに、85点というのは中堅国公立医学部の合格者平均くらいの点数です。
このように、わからない問題があったり時間がかかりそうな問題があったら捨てるようにすると、正解すべき問題で落とすことが少なくなり、結果的に必要十分な点数を取ることができます。
共通テスト英語のリーディングの時短テクニック
テクニカルに時短する方法はそれほど多く残されていませんが、
①状況把握
②質問把握
③速読
この中で一番重要なのは「②質問把握」です。何が問われているかを把握した上で文章や資料を読むことができると、非常に速く解き進めることができます。
また、選択肢同士の違いを先に確認することも重要です。問題文だけでなく、選択肢同士の違いから、どの点に注目して問題を読んだらいいかをさらに精緻にするのです。
共通テスト英語のリーディングで2択で迷った場合
2択で迷った場合、そこでスタックするのは非常に危険です。後の問題に影響が出てしまうからです。
まずはどちらを選び、マークしてしまうことが重要です。ここは「エイヤ」で決めていいです。ただし、問題番号に2択で迷ったことがわかるように印をつけておき、ひと通り解き終えてから戻ってこれたら戻ってくるようにしましょう。少し時間をおくとフレッシュアイズで見ることができ、改めて精査することができます。戻ってくる時間がなくてもどちらかにマークしているので、正解している可能性もあります。
やってはいけないことは、
・どちらにもマークしないでおき、結局戻ってくる時間がなくて不正解になってしまう
・その問題でスタックしてしまって時間をかけてしまい、後半で焦って文章が頭に入ってこずボロボロになる
です。これは英語に限らず他の科目にも言えることです。
共通テスト英語のリーディングのグラフ問題の解き方
グラフは、何が問われているかによって見るべき箇所や観点が変わってきます。よって、グラフ問題こそ、①状況把握(=何に関するグラフか、横軸と縦軸は何か、など)を終えた後は、②問題把握をし、問われていることが何か、グラフ同士のどこの違いに注目すべきかを確定させた上で、問題を解いていくのです。
共通テスト英語のリーディングでは先に問題や選択肢を読むべきか?
一番最初に見ても意味がわからないので、以下の順番を守ります。
①状況把握
②質問把握
③速読
つまり、①状況把握をしてから、②質問把握(=問題文の確認、選択肢同士の違いの把握)を行いましょう。
共通テスト英語のリーディングでは印をつけるべきか?
よくディスコースマーカーにチェックをしましょう、という読解方法が提唱されていますが、そういった小手先の手法が有効なのは中学校までで、共通テストの英語でそのような手法は通用しません。別に「But」の後に重要な内容が書かれているとは限らないのです。
もちろん、問題によっては、ポイントとなるキーワードだったり数字に印をつけておくことが有効であればやりましょう。問題によって臨機応変に対応すべきであって、「必ずこの接続詞があったら印をつけましょう」などといったアドバイスはありませんし、そういった無意味なアドバイスは聞かないようにしましょう。
共通テスト英語のリーディングでスラッシュリーディングはすべきか?
スラッシュリーディングはやることが目的になっている人が多いので不要です。もちろん、主語が長かったり、節や句が長い場合には使えばいいですが、スラッシュリーディングすることで魔法のように読解しやすくなるということはありません。
共通テスト英語のリーディングでケアレスミスを防ぐ方法
間違った選択肢を選ぶことはケアレスミスではありません。単なる実力不足です。
共通テスト英語のリーディングにおけるケアレスミスは「マークミス」くらいでしょう。マークミスを防ぐ方法は、全科目で共通していますが、「解答番号を毎回確認する」以外にありません。
なお、マークはある程度はまとめて行っていいと考えています。必ず1問解けたらマークする必要はなく、一定の塊までいったらまとめてマークするのがいいです。理由としては、
①マークする際は解答番号を毎回確認する、がルールなので、1問ずつマークしていると時間のロスが大きい
②せっかくスイスイ解けているのに手を止めてマークするのは煩わしい
③まとめてマークした方がマークミスは減る
といった理由からです。
一方で、あまりに溜めてしまうと、最後にマークができずに時間切れになってしまうという最悪なケースもあり得るので、その点には注意しましょう。
共通テスト英語のリーディングの見直し方法
共通テスト英語のリーディングに限らず、共通テストという時間がタイトな試験において、「最後に見直す」という概念は持たない方がいいです。見直しをする前提で雑に解き、結局戻れずにタイムアップになってしまったら最悪です。
共通テストでは、各問題で確実に間違えていないことを確認して進めていく、というのが原則です。その選択肢を選んだ理由や根拠となる箇所があることを確認し、これで間違えてないということを確認した上で選択肢を選んだり、マークする際には解答番号を必ず確認するなどしましょう。
「マークミスがあるか最後の見直しで確認したらいい」などと考えるのは絶対にやめてください。マークミスを見つけたのに時間がなくて直せなかった、ということに絶対になります。
共通テスト英語のリスニングの解き方にコツはある?
共通テスト英語のリスニングでは、リーディング以上に、以下の2つを意識することがコツです。
①状況把握
②質問把握
よくある失点原因は、質問把握をせずにリスニングし、問題文や選択肢を見たとき「あれ、こんなこと聞かれてたんだ」「その点に注目して聞いていなかったからどれを選んだらいいかわからない」といったものです。
そうならないよう、必ず先に問題文と選択肢(=選択肢同士の違い)を確認し、注目して聞くべき箇所がわかっている状態で聴くようにしましょう。
共通テスト英語のリスニングでは最初に選択肢に目を通すべきか?
はい、必ず目を通しましょう。
共通テスト英語のリスニングで集中力を持続する方法
練習あるのみと考えています。共通テスト英語のリスニングは第一日程の最後に行われるもので、疲労困憊しているときに集中を切らさず最後まで聞くのはなかなか大変です。しかし、この集中力を本番だけで発揮しようと思ってもまず無理です。
実力さえあれば、たとえ疲れていても英語は聞き取れます。発想を変えて、どんなに疲れていても英語の内容が理解できる実力をつける、練習しておく、ということを重視しましょう。
共通テスト英語のリスニングで聞き逃した場合の対処法
聞き逃したりわからないものがあったら、潔く諦めるのが肝心です。リスニングが聞き取れなかったり、選択肢が絞れなかったりすると、結構焦るものです。しかし、問題はどんどん先に進んでいきます。その問題で失点しても傷は最小限にとどまりますが、次の問題以降にも影響が及ぶと大事故となります。
聞き逃した際に潔く諦め、次の問題に頭が切り替えられるよう、現実的な目標点を明確に決めておき、何問なら失点してもいいということを認識しておくとよいでしょう。リスニングは多くが3~4点ですので、85点目標なら4~5問は落とせます。わからない問題が4~5問あると体感は非常に焦りますが、それでも85点は出るのです。
上記のような心持ちで共通テスト英語のリスニングの演習をし、焦らない練習をしておきましょう。
すべては練習で決まります。練習時点で結果は決まっていると考えていいので、万全の体制で臨めるようにしましょう。