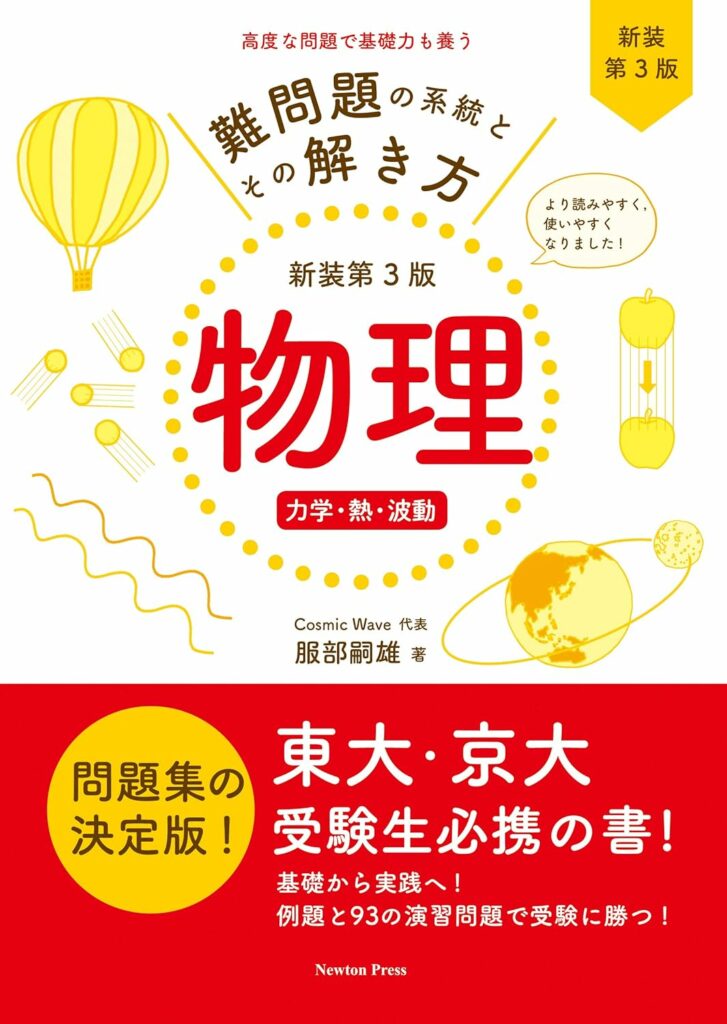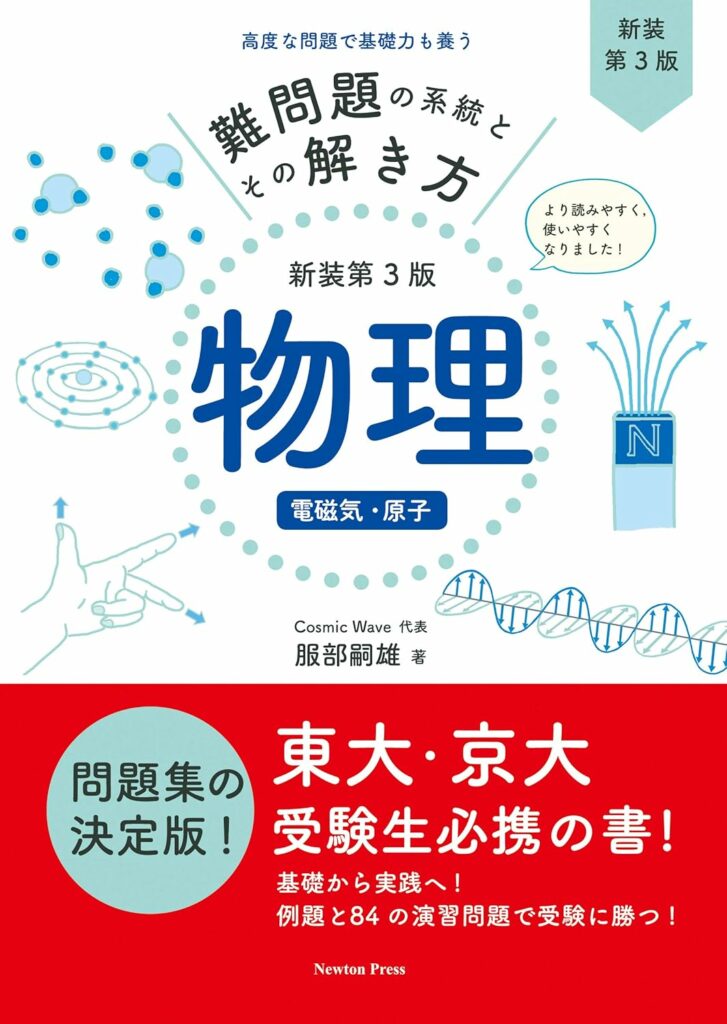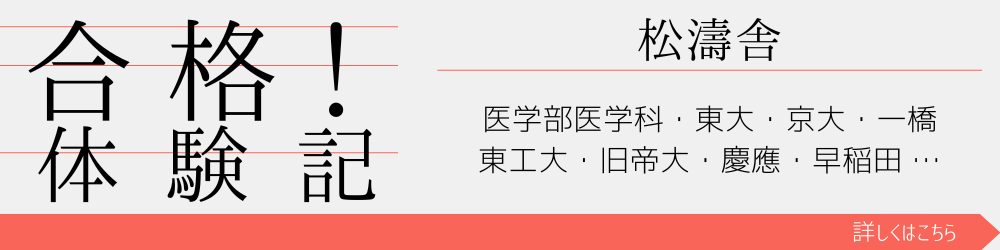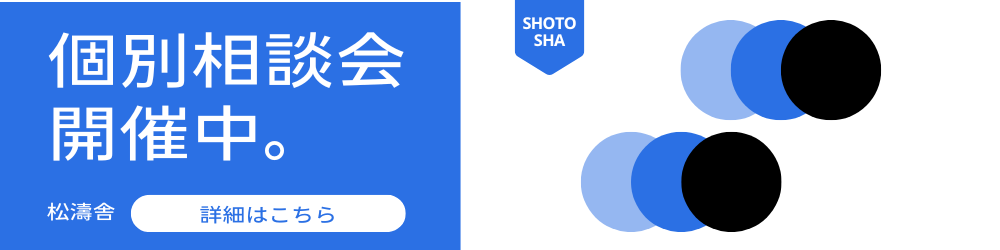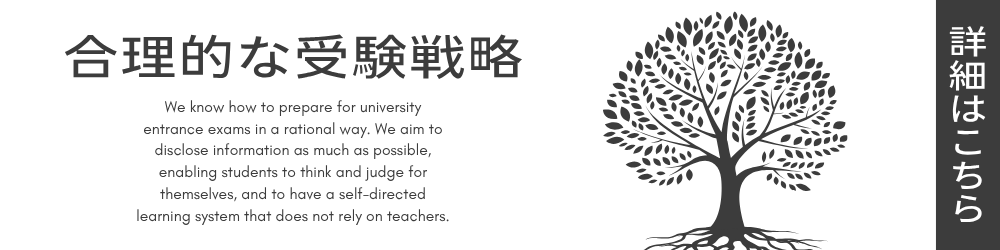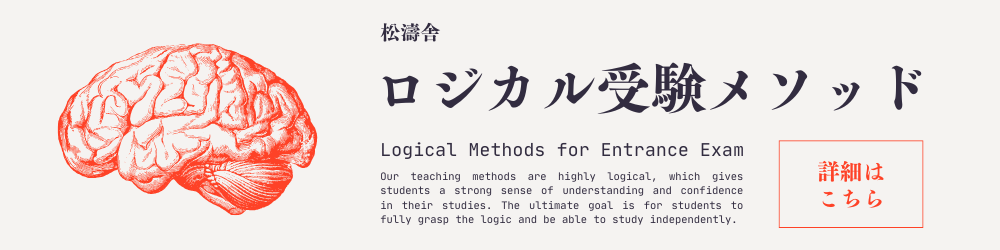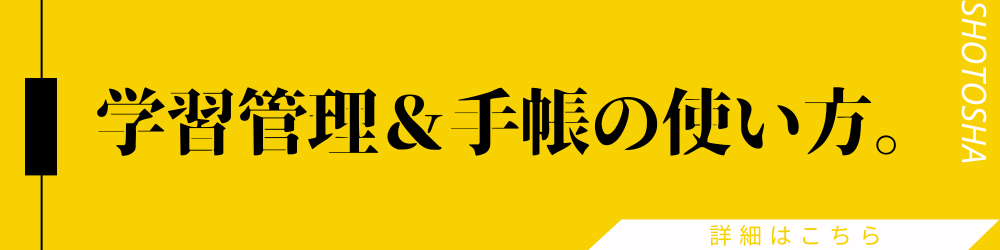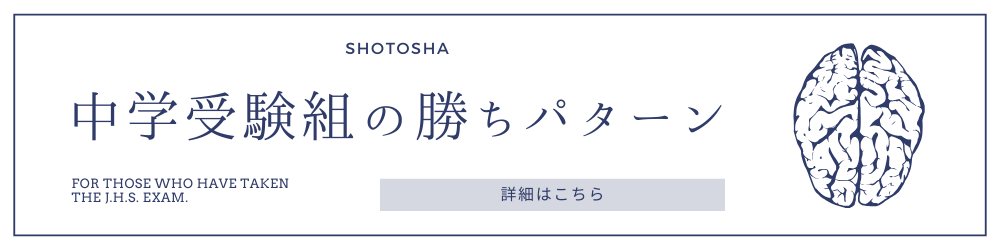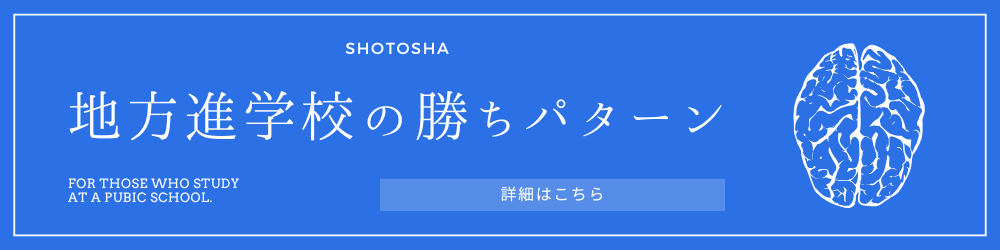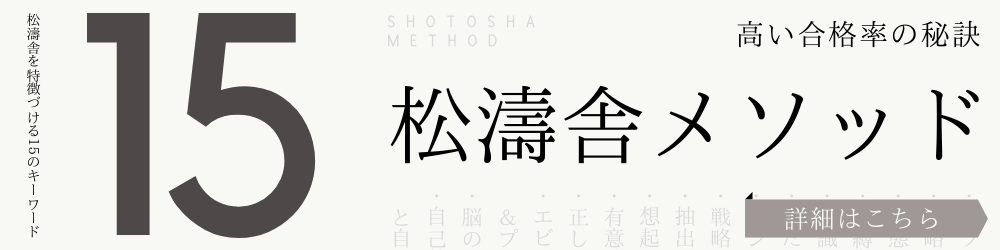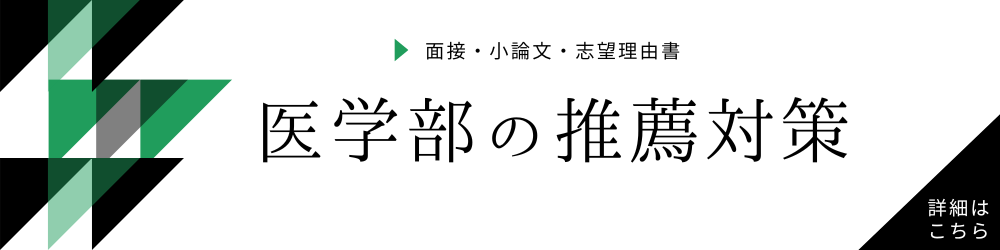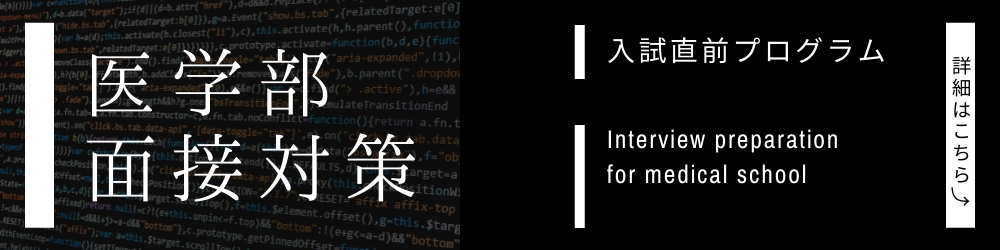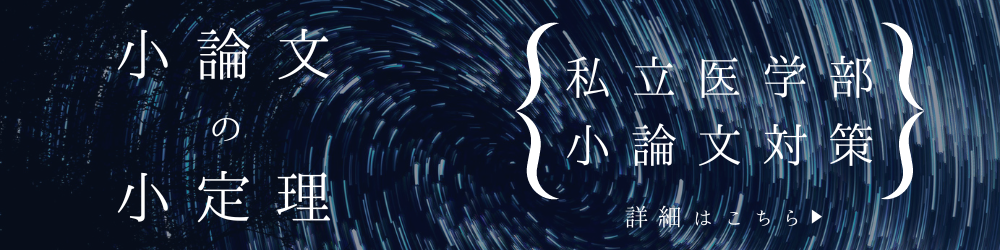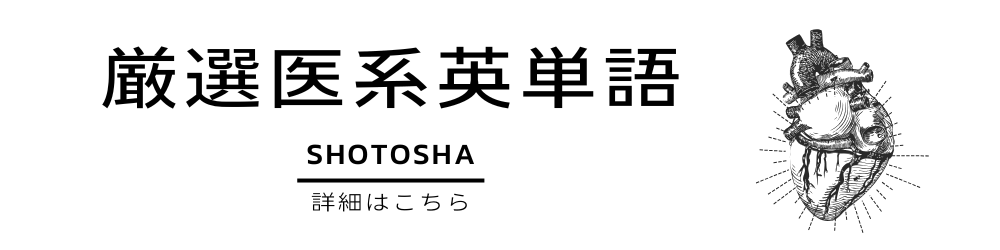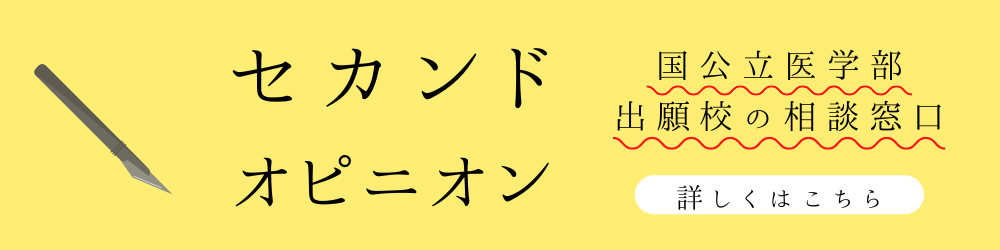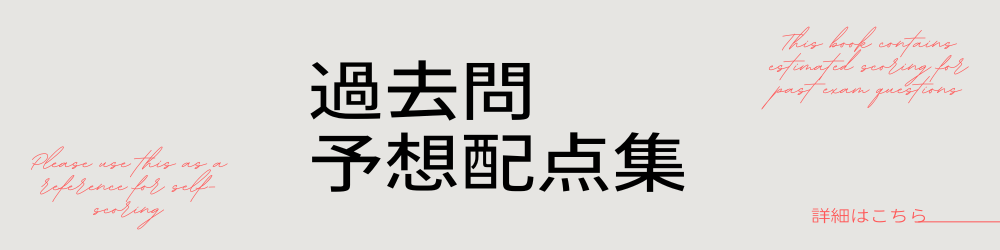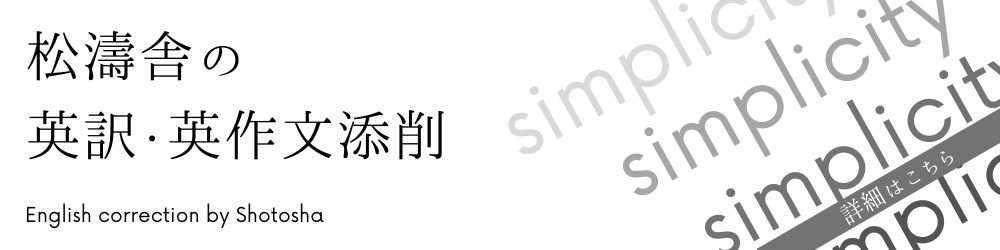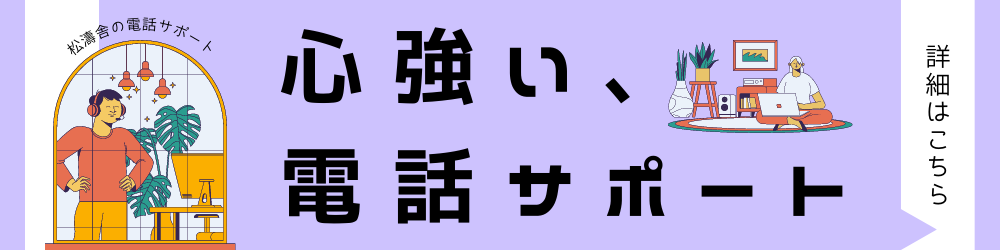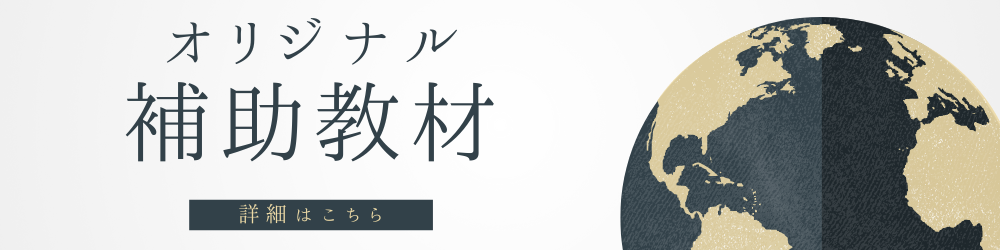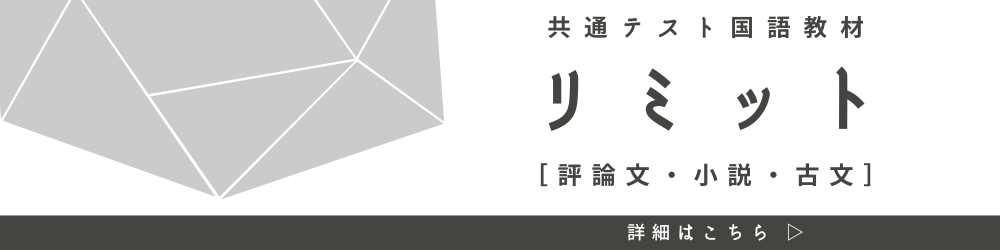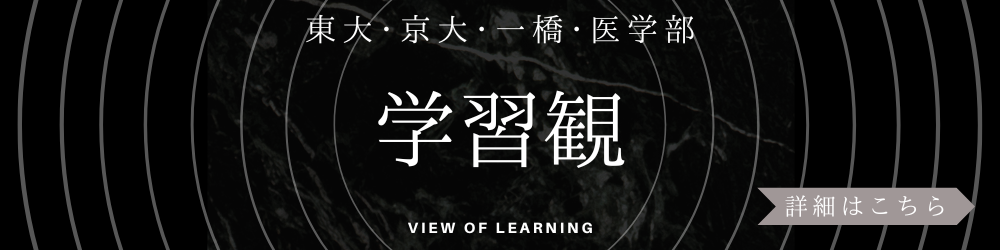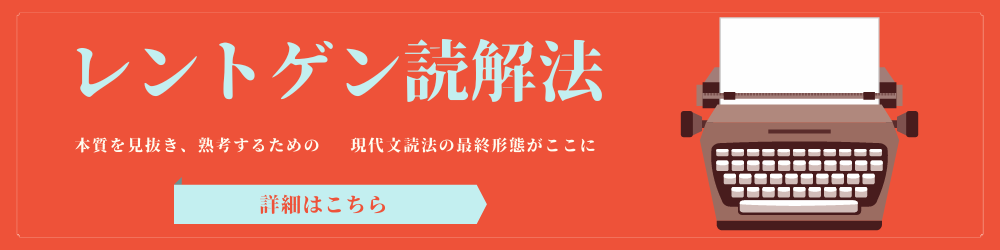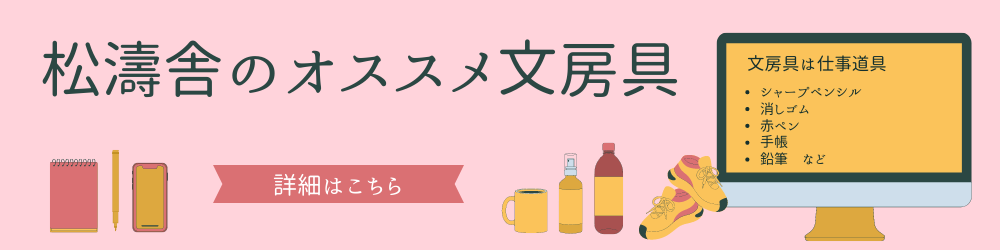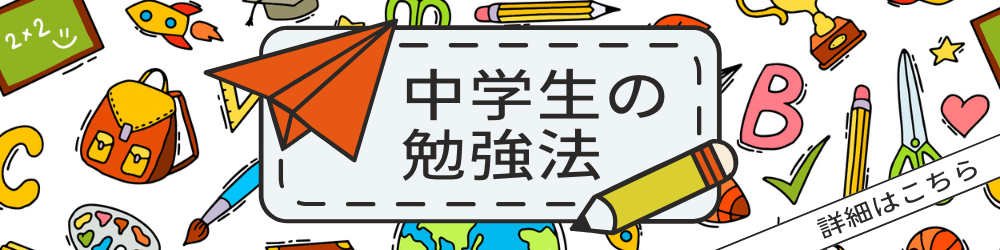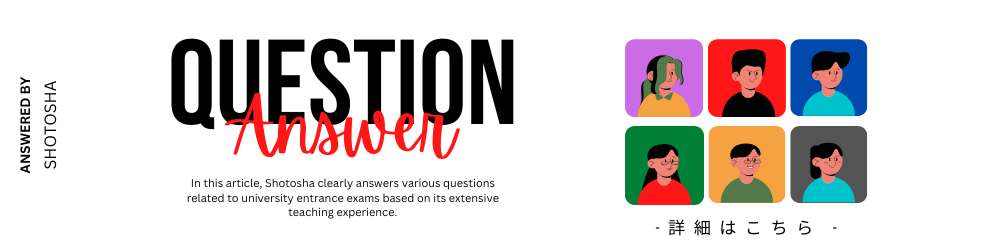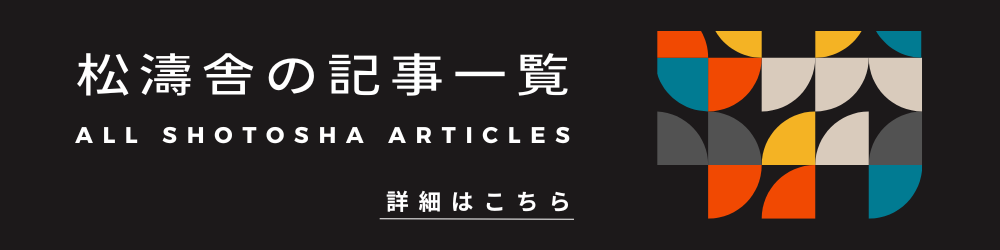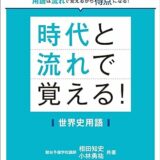『難問題の系統とその解き方』で合格可能な医学部・上位校
松濤舎での合格実績を以下に記載します。
・医学部医学科
大阪大学、東京科学大学、千葉大学、横浜市立大学、筑波大学、広島大学、金沢大学、新潟大学、熊本大学、信州大学、岐阜大学、浜松医科大学、鳥取大学、愛媛大学、大分大学、福島県立医科大学、群馬大学、高知大学、宮崎大学、香川大学、富山大学、弘前大学、秋田大学、慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学、順天堂大学、日本医科大学、国際医療福祉大学、自治医科大学、昭和大学、東京医科大学、東邦大学、日本大学、聖マリアンナ医科大学、東海大学、帝京大学、東京女子医科大学、埼玉医科大学 ほか
・他学部
東京大学、京都大学、大阪大学、名古屋大学、北海道大学、東北大学、一橋大学、神戸大学、慶應義塾大学、早稲田大学 ほか
※代替可能な問題集を使った合格実績も含む。
『難問題の系統とその解き方』の習得レベル
レベル1:5割の例題を、手を止めずに、自力で解くことができる。
レベル2:8割の例題を、手を止めずに、自力で解くことができる。
『難問題の系統とその解き方』の使い方
例題を見て解けるか確認し、できなければすぐに解説を読んでください。
初めから自力で解ける必要はありません。。
解説を読む過程で理解を深めながら、最終的に該当問題が頭に入ったらOKです。
『難問題の系統とその解き方』の前にやるもの
東大理Ⅲ、京大医学部、阪大医学部、慶應医学部以外は『名問の森』までで十分です。
『難問題の系統とその解き方』の次にやること
過去問演習に入ってください。
『難問題の系統とその解き方』に関する前提
本書は、東大理Ⅲ、京大医学部、阪大医学部、慶應医学部を目指す生徒のみが対象です。それ以外の志望者には本書は不要です。また、例題以外は解説が少ないため、例題だけを解けば大丈夫です。
【決定版】物理の完全攻略法
医学部・上位校受験生向けに物理の勉強方法と年間スケジュールをまとめました。参考にしてみてください。
『難問題の系統とその解き方』に関するQ&A
- 『難問題の系統とその解き方』の使い方は?
- 本書は、例題を見て解けるか確認し、できなければ解説を読むことが推奨されています。初めから自力で解ける必要はなく、解説を通じて理解を深めることが重要です。
- 『難問題の系統とその解き方』の習得レベルは?
- 本書の習得レベルは、レベル1が5割の例題を自力で解けること、レベル2が8割の例題を自力で解けることです。これにより、受験に向けた基礎力を養います。
- どのような学生が『難問題の系統とその解き方』を使うべきか?
- 本書は、東大理Ⅲ、京大医学部、阪大医学部、慶應医学部を目指す生徒向けです。それ以外の志望校の生徒には必要ないとされています。
- 『難問題の系統とその解き方』の前にやるべき参考書は?
- 本書の前には『名問の森』までの学習が推奨されています。特に難関校を目指さない場合、これで十分です。
- 『難問題の系統とその解き方』の次にやるべきことは?
- 本書を終えた後は、過去問演習に進むことが勧められています。実践的な問題を解くことで、受験対策が強化されます。
- どのように『難問題の系統とその解き方』を活用すれば良いか?
- 例題を解く際は、まず自分で考え、解けなければ解説を読むことが重要です。これにより、理解を深めることができます。
- 本書の解説はどの程度詳しいのか?
- 本書は例題に対する解説が中心で、詳細な解説は少ないです。例題を重点的に学ぶことが推奨されています。
- 『難問題の系統とその解き方』の特徴は?
- 本書は難関大学受験に特化した問題集であり、例題を通じて論理的思考を養うことが目的です。
- 受験勉強における『難問題の系統とその解き方』の位置付けは?
- 本書は、難関大学を目指す受験生にとって、実践的に問題を解く経験を積むための重要な教材です。
- 『難問題の系統とその解き方』を使う際の注意点は?
- 本書は特定の大学を目指す生徒向けであり、他の志望校の生徒には不要です。使用前に自分の目標を確認することが大切です。